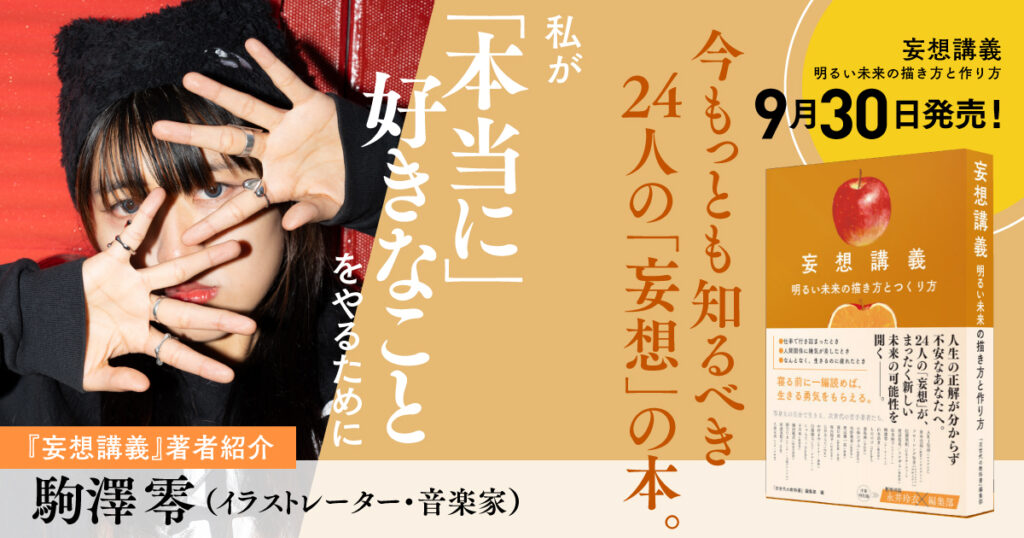現在、本記事の新規販売(決済)は停止しております。
すでにご購入済みのお客様は、引き続き記事内のログインボタンより閲覧が可能です。
絵描きとして活動している筆者は、日常に潜むこうした何気ない既視感や、ついつい無視してしまうような感覚に着目して、作品を制作しています。過ぎ去った一瞬の感覚や情景を作品に繋ぎとめて、また取り出せるように保存する作業は一見すると特殊な技術が必要なように思えますが、これは何も絵が描けなければできないことではありません。
小学校の宿題で絵日記があったと思いますが、自分には絵のセンスがないなあと思っても、あったことを書きとめることは出来たでしょうし、文章にまとめるのが苦手な人も、家族や兄弟、友達に思ったことや今日あった出来事を話したことはあると思います。みんな気づいていないだけで、各々その人に合った形で、その人なりの感覚を得て生きている。
今回「妄想」というテーマを頂いたときにわたしが思い出したのは、フランスのことわざ”Un ange passe[1]“=「天使が通る」になぞらえてわたしが”天使”と呼んでいる、日常生活の中でふと感じるキャラクターの所在や、どぎまぎするような誰かの足跡のことでした。
この文章では、わたし自身の経験をベースに、生活の中の「妄想」について考えていこうと思います。
そもそも、「妄想」とは何だろう?
広辞苑第七版[2]で妄想という言葉の定義をひくと、以下のように書かれています。
①[仏](モウゾウとも)みだりなおもい。正しくない想念。徒然草「所願皆─なり」②[心]根拠のない主観的な想像や信念。統合失調症などの病的原因によって起こり、事実の経験や論理によっても容易に訂正されることがない。「誇大─」「被害─」「関係─」
①で触れられているように、もともと「妄想」という単語はサンスクリット語[vikalpa(ヴィカルパ)]の訳語で、正しくない推量的な判断、間違った判断を表します。日本語ではこれが転じて、②で書かれているように、統合失調症に代表されるような「ありえない考えを本気で信じこみ、おかしいと指摘されても、決してその考えを曲げない」という行動を指して使われています。
精神医学における統合失調症の症状における妄想はいくつかありますが、他人が自分を害しようとしていると思いこむ「被害妄想」や周囲の出来事を自分に関係づける「関係妄想」、さらに、何かに追われていると考える「追跡妄想」、誰かに見張られていると考える「注察妄想」、自分が特別な血筋だと思い込む「血統妄想」、家族が本当の家族ではないと思い込む「家族否認妄想」、自分を偉大な存在だと信じ込む「誇大妄想」、異性に愛されていると思い込む「恋愛妄想」などと、かなり幅広い種類が存在します。[3]
しかし、「関係妄想」や「誇大妄想」と言われてしまう感情は軽度ならば試験や目標に向けて努力するために良く働くこともあるでしょうし、「恋愛妄想」は誰しも恋愛初心者の頃はすぐに勘違いしてしまいかねません。また、宗教的な思想や文化的な背景という根拠があれば、おそらく統合失調症の一症状である「幻声」「幻覚[4]」によって作られた「神のお告げ」がひろく受け入れられるシチュエーションもあります。
同様に「妄想」として扱われるものとしては、陰謀論、マインドコントロール、カルト宗教などが挙げられます。統合失調症の妄想が病気の症状であるのに対し、これらの妄想は心理学的手法を用いて他者から誘導され、形成されるものですので、妄想というより「思い込み」「信仰」といったニュアンスの方が正確かもしれません。
なぜ今、「妄想する力」が必要なのか
禅の言葉に「莫妄想(まくもうぞう)」という言葉があります[5]。これは「妄想するな」という意で、仏教用語で「正しくない推量的な判断、間違った判断」とされているvikalpaを禁じる意、つまりはプラスマイナスに関わらず、「未来の解らないことをあれこれ考えることをやめろ」という教えになります。
これは先のことを深く考える時間があったら今を一生懸命に頑張ろう、という意味の単語でわたしも凄く好きなのですが、現代日本社会においてはすこし危うい発想だと思っています。
昭和から平成初期にかけてテレビ放送が覇権を得ていた頃は、国民的アイドル、国民的ヒットソングといった、本当に全人口の誰もが知るようなコンテンツが今とは比べ物にならないほどたくさん存在していました。エンターテインメントは人々の日常とはまったく別世界で、事務所やコネクションなど、莫大な資金源と環境、パイプがなければ世の中に知られる存在になることはきわめて困難でした。そのため、アンダーグラウンドな文化や子供が触れることがふさわしくないとされるコンテンツは資金力によってある程度選別され、ゾーニングされていました。もちろん、セクシー女優からタレントになった筆頭格の黒木香や、1960年代~80年代に放送されていたヌードダンサーが出演したり乳房露出がまかり通っていたりもした「お色気番組[6]」ジャンルなど、一部の例外は存在しますが、「お色気番組」が世間からの圧倒的非難で終了したように、ある程度は視聴者からの自浄作用が発生することでコンテンツの公共性が担保されていたように思えます。
一方で、テレビ的なお約束やパワハラ、過酷な労働環境など諸問題もあったと思いますが、国民的コンテンツがなくなり、誰もが別の方向を向いてエンターテインメントを享受している現代においては、我々は日々ある程度は好きなコンテンツを選択して受け取ることができます。かつてはテレビで見るのが当たり前だった有名芸能人、タレントも軒並みYouTubeをはじめるのが当たり前で、そこでは素人の作った動画も芸能界でずっと活動してきたタレントが出演する動画も同列のものとして我々は見ることができるのです。ひとつの絶対的な覇権というものが崩壊し、各々の世界で各々に向けられたサジェストの中で人気のコンテンツをある程度同列に受容する。こうした構造は、消費者側に高いリテラシーを要求します。
もうすこし具体的に考えてみましょう。
昨今は育児において赤ちゃんや幼児に動画サイトを与えることも珍しくありません。「シナぷしゅ」のように、赤ちゃんに見せることを想定して長尺で毎日動画投稿されているチャンネルもあります。それを受けてか、YouTubeには「子供向け動画」という、一部動画に一定の制限をかける機能が存在します。
ですが、最近は少し規制が厳しくなったとはいえ、同じYouTubeにはポルノすれすれの過激なサムネイルや内容の動画がたくさん投稿されており、制限を外せば誰でもそれを視聴できます。そこまで露骨なものではないとしても、反社会的な内容や夜の世界を描いたコンテンツはいままでテレビでは放送されてこなかったこともあって人気があります。『明日、私は誰かのカノジョ』『東京深夜少女』などが連載される「サイコミ」のような、アンダーグラウンドな内容に特化した漫画が多く掲載されるマンガアプリも人気があります。時を同じくして、地下アイドルカルチャーにおける「推し」文化が一般化したことで、高速で遷移するコメント欄の中で大量の金銭を投じてコメントを読んでもらう「Super Chat」をはじめとした投げ銭カルチャーも当たり前になりました。これも、YouTubeで頻繁に観測することができます。
しかし、推し文化の中で型にはまった応援をすることやコミュニティ内で競争を煽られ、それに応えていくというある種自傷的な趣味はあまり健全ではないし、長期的に続くモノではないと思います。実際、『ガチ恋粘着獣』『推しを愛する私たち~推し×ファン~アンソロジーコミック』など、ファン目線での醜い感情を扱った二次的な漫画も出現し、人気を集めていることから、実は少しずつ消費者の側も疲弊してきて、「推し活」ブームが終息に向かっているのではないかと感じています。
2022年の「推し活にかけるお金と節約に関する意識調査[7]」や2024年実施の「推し活に関する調査 2024年[8]」を見ると、高年齢層を中心に、近年は生活を優先しながら推し活を楽しんでいる人が多い。ですが、10代~20代では他の世代に比べて投じる金額が大きいのも特徴です。女児向け漫画雑誌「ちゃお」のWeb漫画サイトには「推し活」カテゴリの連載漫画が3本あったり、かつて歌舞伎町にいるホス狂の象徴であった「地雷系」ジャンルのファッションは流行しすぎて小学生の服装にまで降りてきています。つい先日も15歳に600万円を貢がせたホストが逮捕[9]されたニュースが世間を騒がせました。視聴者が好きなコンテンツを選択して楽しむ間口が広がり、それまで入ってこなかった面白いコンテンツが増える一方で、若年者にとってはアンダーグラウンドな世界への敷居が低くなってしまうことに繋がっているのではないか、とわたしは危惧しています。
一方で、年配の方への影響もあります。わたしの知人でも、親がインフルエンサー経由で偏った思想を持ちはじめて会話ができなくなった、陰謀論にハマってしまった、という話を聞いたことがあります。この激動の時代においては誰しも強烈なカリスマを求めているのでしょうが、より資本主義が強化され、倫理観が削がれたコンテンツも流入してしまうのが、テレビからYouTube時代へと変化したことの危うさに思えます。1995年に地下鉄サリン事件を引き起こしたオウム真理教の存在ですら、少しずつ世間に忘れ去られつつありますし、よりきちんと自分たちの頭で日々情報を精査し、考えていかなければならない時代が来ています。誰かを推すことは素晴らしいことですが、まず第一に自分の思想を言語化し、肯定して強化することで、はじめて他の人や物事について考えるスタートラインに立てるのではないでしょうか。
でも、ただでさえ学業や仕事で日々いっぱいいっぱいなのに、息抜きの場ですらつねに頭を働かせていなければならないのは疲れますよね。
資本主義が続く限りは、個々人の情報を分析し、パーソナリティや出生、状態に合ったマーケティングが進んでいくことは必至でしょう。それどころかジョージ・オーウェル『1984』や、アニメ『PSYCHO-PASS』で描かれているような管理された監視社会に向かっていく可能性すらあります。伊藤計劃『ハーモニー』で描かれているように、善性によって作られた社会が必ずしも皆の生きやすい社会になるとは限りません。
サジェストは私たちにたくさんの快楽と需要に合った刺激を与えてくれます。しかし、本当にそれだけでいいのでしょうか。自らのために「コンテンツをサジェストしてくれ」と望まなくても、みな平等にマーケティングされる側の人間であることを自覚すること。そして、与えられたものを自分の個性だと信じ込むのではなく、他者や社会に左右されることなく存在する確かなアイデンティティを形成することが重要だとわたしは考えます。